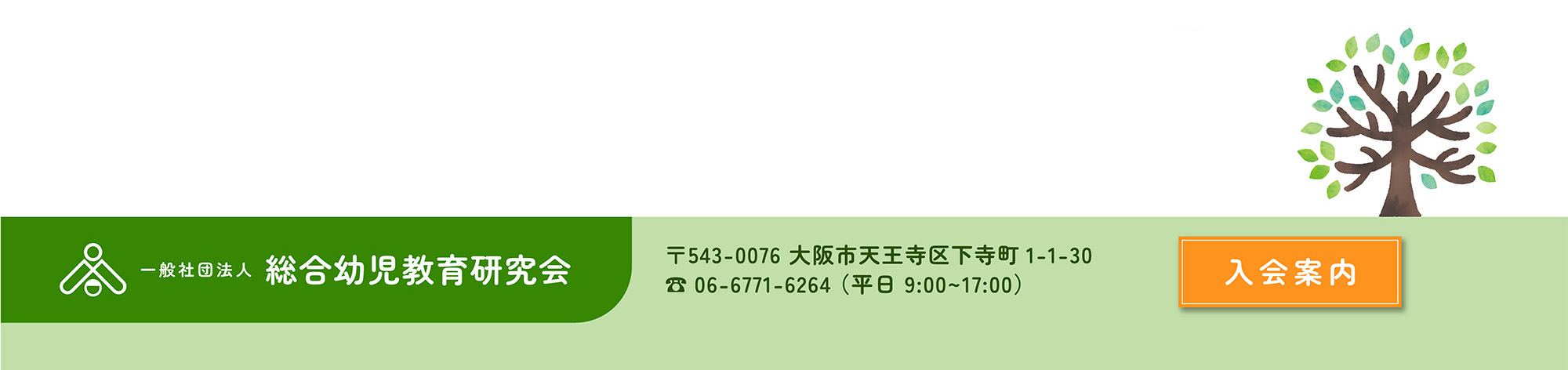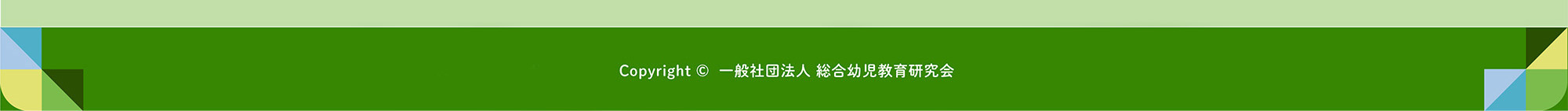■保育者は何を学んでいるのか
2月の全国公開保育では、午後の時間帯を使って、参加した保育者によるグループワーク(以下GW)がありました。あらかじめ用意して、同じ学年の担任同士が車座になって、総幼研の「先生としての心がけ」や、またいくつかの主題について話し合いました。
GW がはじまると、とたんに会場がにぎやかになります。初顔合わせでもあり、60分というわずかな時間だったのですが、それでも同じ総幼研の保育者同士、話は大いに弾んだようです。
最近、保育界でもGWを取り入れる研修の機会が多くなっています。参加者の当事者意識を高め、コミュニケーションを活性化させることが期待されるからでしょう。短い時間では問題解決とまではいきませんが、課題を共有したり、いろんな事例を交換することもできます。似たもの同士ですから、安心があるし、理解が早い。外からの刺激を受けたりもします。
一昔前の研修といえば、講師から一方的に伝授されるものが中心でしたが、学ぶ目的も大きく変わってきているのでしょう。知識や情報の獲得よりも、考え方やシンパシー、関係性といったものをどう高めるかにシフトしているように感じます。「感情労働」といわれる保育者であればなおさらです。
このたびのGW のアンケートでも、「(参加者同士)刺激を受けた」「他園の取り組みが参考になった」「同じ総幼研仲間同士、思いは同じということを共有できた」というものが多数ありました。
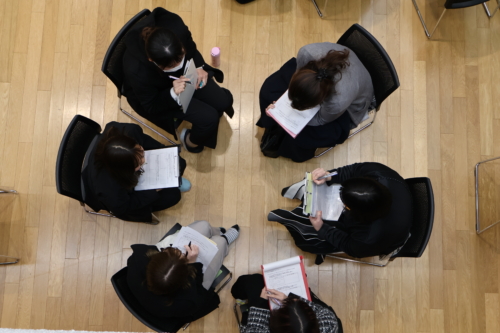
■総幼研という分厚い共通基盤
自園でもGWをされているケースが多いでしょう。同僚は互いを熟知しているので、分かり合える面と、だから故、一定の抑制が入る場合もあります。経験の浅い先生はベテランの先生になかなか本音がいいにくいのではないでしょうか。
その点、今回のような、「未知の他者」とのGWでは直接的な利害関係にないので、よりオープンになることができます。率直に自分の意見をいえるし、また素直に相手を受け入れることができる一面があります。匿名の関係だから可能となるコミュニケーションの利点と言えます。
さらに、当然園種も違えば、地域差もあるのですが、それが反発しないのは、参加者が総幼研という分厚い基盤を共有しているからこそでしょう。ここにも「共感・共鳴・共体験」があります。だから中身のある話し合いが活性化するのです。
GWは、もちろん研修だけの場面に限りません。各園におけるチーム保育や園を挙げての行事などもその真髄でしょう。子ども集団でいえば、日課こそ子どもと先生のGWの結晶といえるのではないでしょうか。
同じ集団に属する人が相互で影響を与えあい、考え方や行動が変化することを、心理学で「グループ・ダイナミックス」といいます。外でも内でも同じ総幼研にかかわる保育者同士、そういうプラスの関係を構築しながら、職場をさらにエンパワーしていきたいものです。