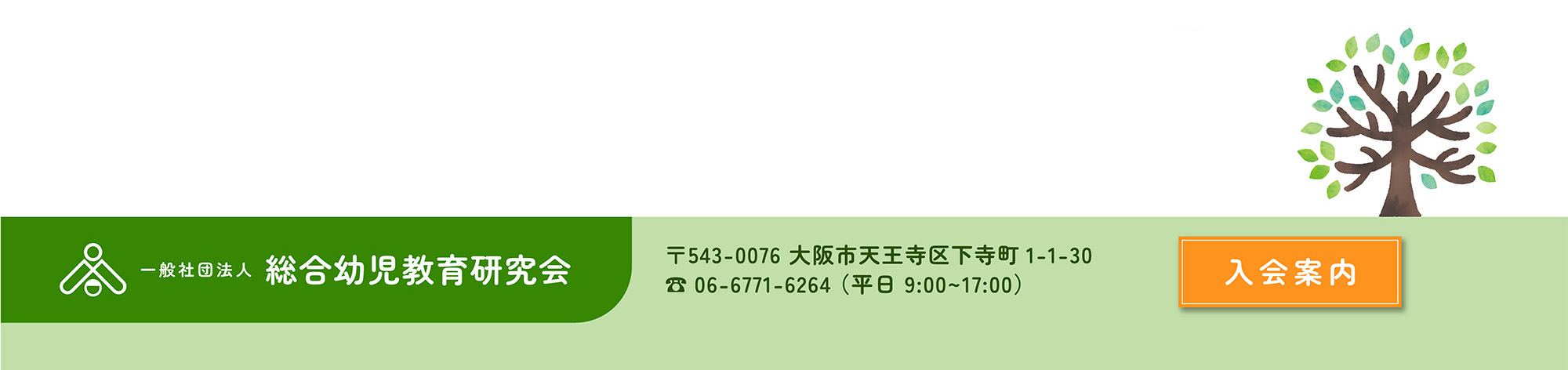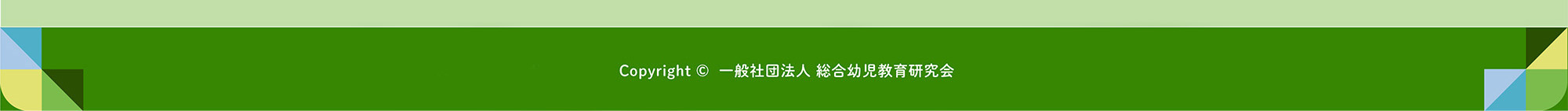■資質か、スキルか
生まれ持った才能や潜在的な力を資質といい、経験や学習を通じて後天的に習得したものをスキルといいます。最近はほとんど同じ意味で用いられるようですが、では、その人らしい「性格」とは資質でしょうか、スキルでしょうか。
たとえば、明るくて周囲を和ませる先生がいたとします。保育者にはよくいるタイプですが、その先生が持ち前の性格を発揮して、学年メンバーの意見をまとめたり、会議の議論が前向きに進むように心配りができたりすると、それは「性格」だからではなく、「調整力」や「推進力」が高いというスキルにあたります。「あの先生は前向きだから」「コミュ力が高いから」というゆるい性格づけではなく、保育者としてのキャリアの正当な評価につながっていきます。
職場としての保育現場には、多様な先生が共に働いています。経験年数、年齢、保育力や理解力、性格など色々な資質やスキルが入り混じっていますが、最もスタンダードな成長モデルは、「経験年数にともない、保育(実技)技能が高くなる」ものでしょう。10年担任をやっていれば、日課を高い水準でできて当然といえます。
しかし、前述のような調整力、推進力といったスキルとなると、話は別かもしれません。経験年数の長い先生だから、会議で意見を調整できる、新しい保育について提案ができる、同僚のモチベーションを上げることができるとは限らないからです。
もちろんどの園も、保育の主任格の先生となれば、経験に裏打ちされた保育技能と、様々なスキルを併せ持つのかと思いますが、これを「その人任せ」ではなく、どのように適正なスキルとして評価し、また育てていくのか、園長にとって大きな課題であると思います。
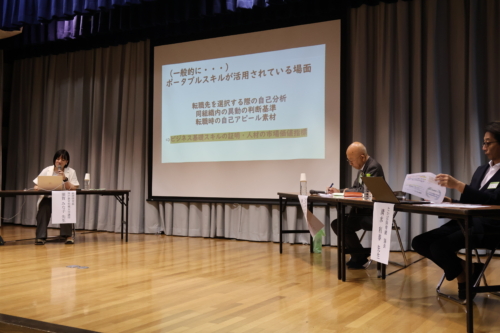
■縦のスキル、横のスキル
最近「人材開発」ということばが多用されるようになりました。「人材育成」とは、個々の職員の成長を目指すものですが、「人材開発」は、組織全体の成長を視野に入れ、戦略的に職員の能力を引き出すものとされます。ひとりのカリスマ保育士を育てるのではなく、チームとして同僚が学び合う環境を目指すべきなのでしょう。「保育マネジメント」が重要視される所以です。
総幼研教育は、特に実技では、多くは経験を重ねるごとに上達していきます。マニュアルもあるし、研修会も充実している。その意味では「人材育成」には適切なのですが、それと「人材開発」は別物と考えるべきです。それぞれが職場で培われた能力を、園や同僚(組織)のためにどのように発揮できるのか、またどのように運用していくかには、園長や保育主任のトップマネジメントが不可欠です。
先日の園長研修会で、総研研究員の須賀みな子先生から、こう教わりました。
「保育現場に必要な同僚性とは、縦のスキルと横のスキルで高め合うものです。縦とは経験値によって向上するスキル(保育技能)であり、横とは、経験値によらないポータブルスキル(発想力や対応力、コミュ力やパーソナリティ等)であり、その双方による相乗効果」が学び合う組織へとつながる、というものでした。
皆さん、職員室を見回してみましょう。まだまだ身近なところに眠っているスキルがたくさんあるのではないでしょうか。
(本稿は7月9日園長研修会にて行われた須賀みな子先生の講演を参照させていただきました)