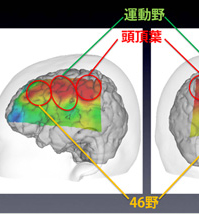まだ少し先だが、パドマ幼稚園で運動会の練習が始まった。競技や演目ではない。開会式の行進、整列、体操など、毎日の朝礼時で、少しずつリハーサルを重ねる。
体育の教師が、朝礼台に立って、お辞儀の手本を見せる。「一、二、三…」。タイミングに合わせて、400人の園児が一斉にお辞儀をするのだが、大人の号令もなく、指図もなく、整然と頭を下げる幼児の姿に、なぜか胸を打たれる。
お辞儀という作法について、調べればいろんな話題が出てくる。お辞儀は、頭頂部を相手に晒すことで、敵意のない…
ことを表す最敬礼だとか、高温多湿な日本では、握手やハグのような肌接触を嫌い、この作法が定着したとか…そんなことは調べればわかる。
私が幼児の一斉のお辞儀に感銘するのは、公務員のそれとも、新入社員のそれとも違って、ここに意図や作為を超えた、人間関係の原風景が窺えるからだ。
齋藤孝は「型や基本は、本質の凝縮である」といっている(「身体感覚を取り戻す」)。そもそも礼法とはすべてそういうものだが、生まれたまだ4、5年にしかならない幼児の型とは、型文化に馴染む以前の型である。言うまでもないが型とは古典であり、また強制力によって習わされる。ここにお辞儀という型の教育概念が生まれるのである。齋藤はこうも書いている。
「自分の人生の連なりを証明する道の存在は、生きている意味の実感につながる。幼少期の自分が老年の身の内にも生き続けているという実感によって、生は肯定される」
齋藤はこれを「身体知としての教養」として、古典の暗誦・素読について述べているのだが、「暗誦は言語の原風景づくり」というフレーズになぞらえば、幼児のお辞儀とは、「人間関係の原風景づくり」といえるのではないか。相手への尊重とも敬意ともいえるし、自分自身への謙虚とも遠慮ともいえる。忘れがちな風景が、垣間見えるのではないか。
人はいったい、誰に対しお辞儀をするのだろうか。お辞儀をしている幼児本人よりも、私は子どもの頭頂部が向いているその先にいっそうに関心が向く。われわれは十分それに値する存在なのだろうか。