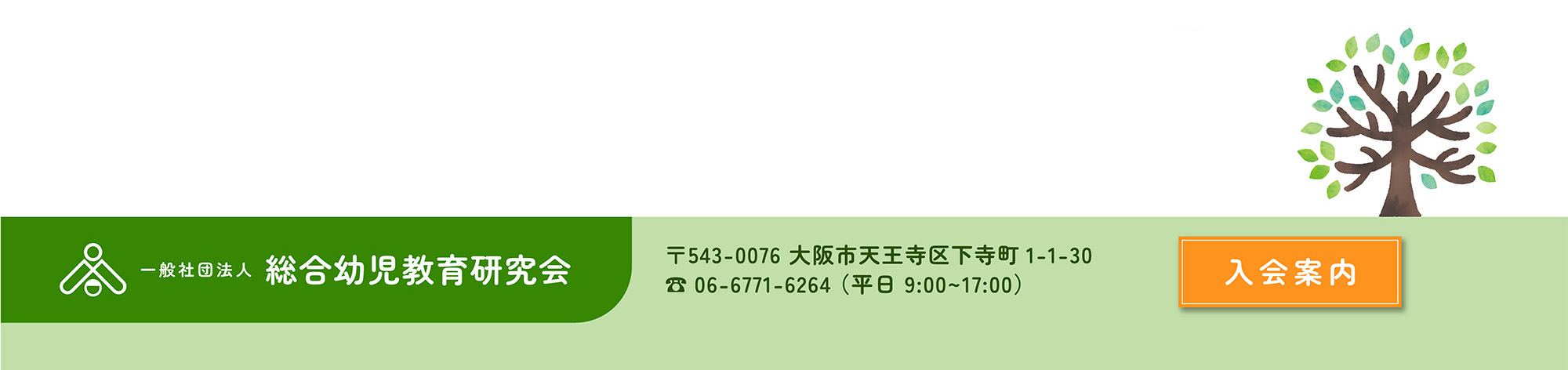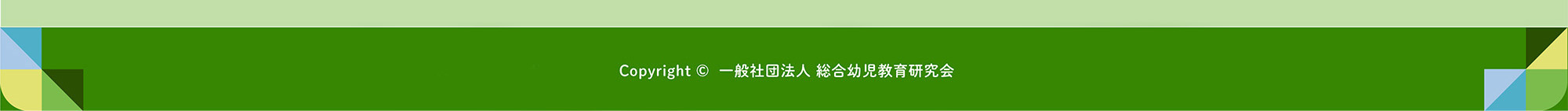秋田光彦会長の教育コラム– category –
-

ことばがけのレッスン。まず大人のことばの感性を磨くことから。
ある食育の勉強会で、講師の先生の「幼児の味覚は,親のことばがけで作られる」というお話に強い印象を受けました。子どもの味覚と言葉は最初から一致しているわけではない。甘い、苦い、酸いなどは、一緒に食事をする大人が「甘いねぇ、おしいね」と共感... -

羊水の海へ。初夏のプールあそび。
先週末、3階屋上プールの大掃除を先生たちと行いました。側面のカーテンが開いた時の見晴らしは、青空と緑とお寺が(さらに奥にはハルカスが)奏でる「絶景」です。いよいよ今週はここで、こどもたちの歓声と水しぶきが上がります。ところで、なぜ子ども... -

最初に、音楽があった。信頼を築く交流の原点とは。
まずは熊本地震で被害にあわれた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。入園・進級して3週間が経ちました。初めての園生活、クラスの仲間との関係づくりにおいては、いかに信頼のコミュニケーションを交... -

震災5年目。人間の基礎基本とは何かを考える。
今日、東北の大震災から5年めを迎えました。被災地ではいまなお、不自由な生活を余儀なくされている人も多く、その傷跡は深く人々の心に残ったままです。 5年を経て、「教育」とは何だろう、と改めて問わないではいられません。自然の脅威を前に、人... -

身体から学ぶ。総合幼児教育の極意とは。
先月の23日、東京で教育シンポジウムに参加してきました。教育財団である前川財団が主催、その趣旨に賛同して、本会も早稲田大学とともに後援に名を連ねました。 シンポジウムは「からだを育てる感覚を磨く」というタイトルのもので、京都大学名誉教授... -

子どもの身体感覚。みんなで動くからたのしい。
当たり前のことですが、 身体機能は、使わないと劣化します。子どものからだの異変、自律神経失調症や異常体温、浮き指や扁平足など、さまざまな問題は、要するには、子どもの時に使うべきからだを十分つかっていないから。汗をかかないから、自分で体温... -

声と身体。教室こそ共振する場。
当会の保育の特徴のひとつは、子どもたちの声です。うただけでなく、音読、素読、暗誦、数唱、ほとんど場面で声が前面に出る。活力のある声です。 かつて教育学者の齋藤孝さんがパドマ幼稚園の子どもの声を称して「ホースに息が通る」と表現しましたが... -

よき集団は、子どものつながりの中から生起する。
小学生の暴力行為が増加しています。文科省の「児童生徒の問題行動」(2014年度)で明らかになりました。中高生はやや減少しているのに、小学生は1万1468件と前年度を500件以上上回っているといいます。 新聞報道ではいろいろな要因を挙げています。少... -

日本式教育を輸出する。生かされている感覚。
私のパドマ幼稚園に勤務する英語講師ウイル先生は、10年以上の教育歴を持ちますが、はじめて日本の学校教育を見た時、違和感をおぼえたといいます。たとえば、朝礼、ラジオ体操、掃除、運動会等々、子どもたちの集団が統率のとれた動きをする。現在で... -

「自然体」は放っておいて育たない。健康な足形をつくる。
東京のある小学校の調査で、足の指が地に着かない「浮き指」の児童が8割を超えたといいます。扁平足の子どもも指摘されていますが、現代の子どもの姿勢に異変が起きています。 小学校の朝礼(15分)で、まっすぐ立つことができず、上半身をふらふらさ...